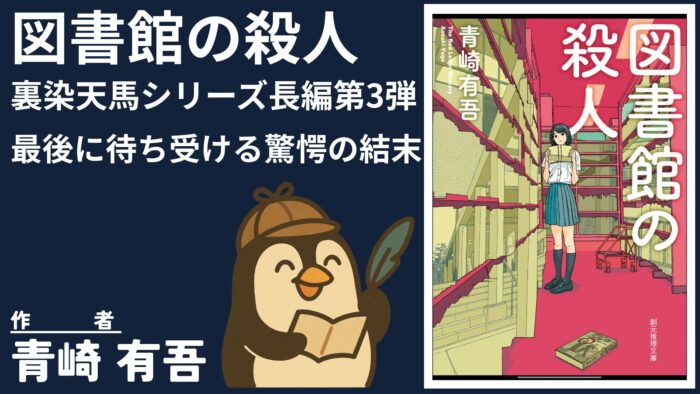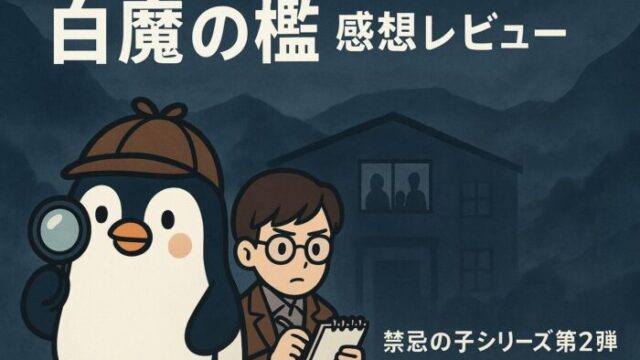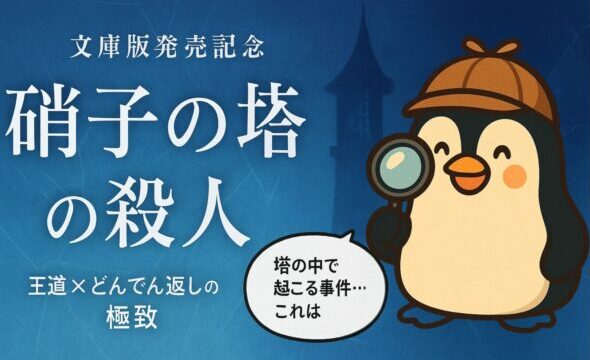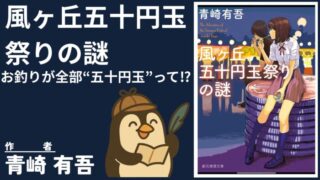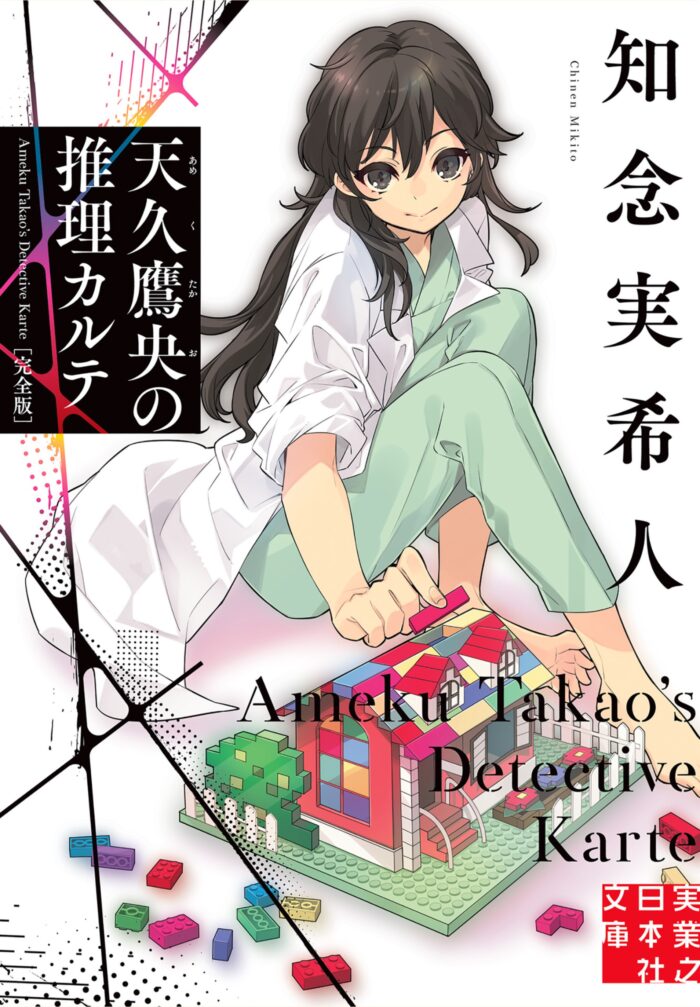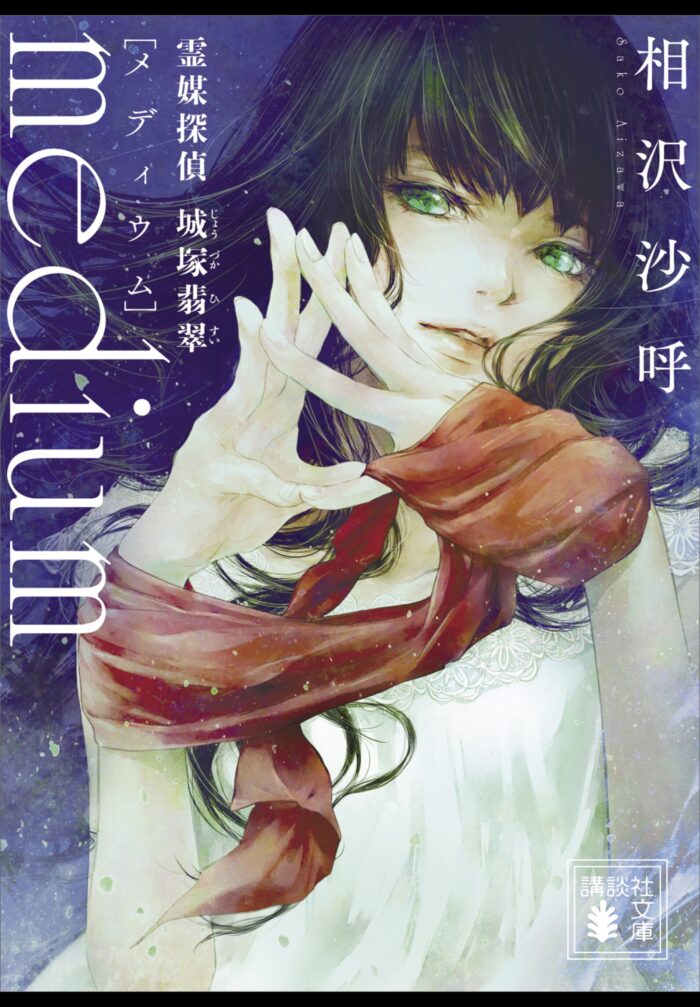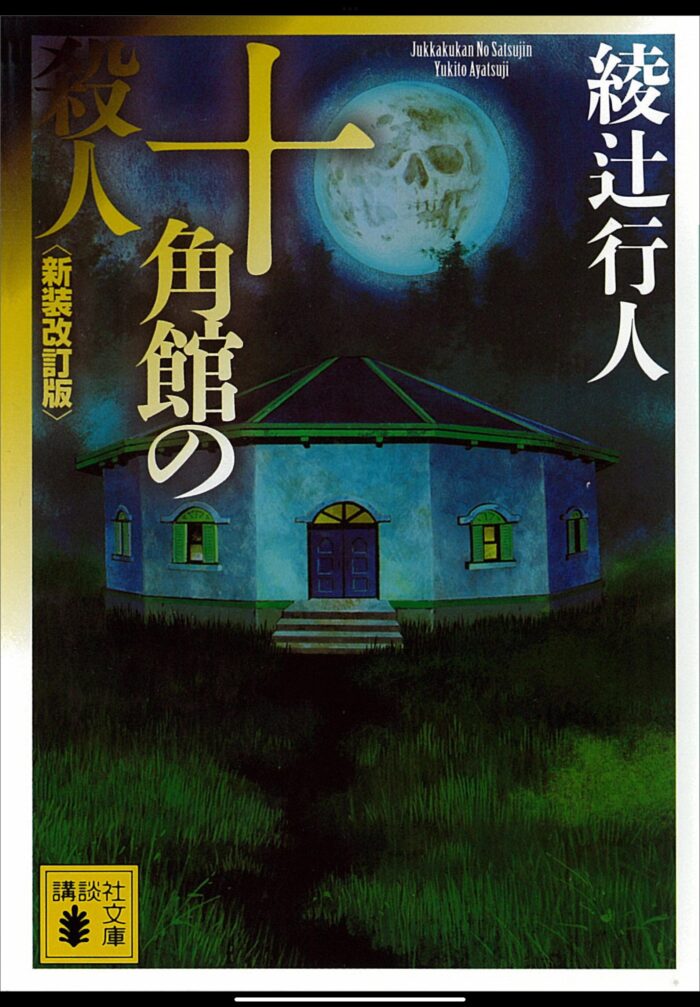山田ぁ……今度は“図書館”で殺人事件だぴよ📚💥
本の匂いと静けさに包まれた場所で、血の文字が残されていたのだ……!
現場に残されたのは、2つのダイイングメッセージ。
しかも、それぞれが“矛盾している”……。
裏染天馬の論理が、沈黙の館に響くときだな。
図書館×ダイイングメッセージ──
これはまさに、“静寂の中のロジックショー”ぴよ🧩✨
ページをめくる手が止まらないのだ……!
📚あらすじと書籍紹介
本格度、青春度、マシマシ!
本で撲殺された被害者が残したダイイングメッセージ
“駄目人間”裏染天馬が導き出す怒濤の推理
9月の朝、風ヶ丘図書館の開架エリアで死体が発見された。被害者は常連利用者の男子大学生。閉館中の館内に忍び込み、山田風太郎の『人間臨終図巻』で何者かに撲殺されたらしい。現場にはなんと、二つの奇妙なダイイングメッセージが残されていた! 警察に呼び出された裏染天馬は独自の捜査を進め、一冊の本と一人の少女の存在に辿り着く。一方、風ヶ丘高校では期末テストにまつわる騒動が勃発。袴田柚乃たちは事件とテストの両方に振り回されることになり……。ロジカルな推理と、巧みなプロットで読者を魅了する〈裏染天馬シリーズ〉第4弾。
解説=佐々木敦Amazonより
作 者:青崎 有吾
出版社:東京創元社
発売日:2018年9月12日
📖 『図書館の殺人』
裏染天馬シリーズ、今回もやってくれたぴよ……!😳💥 「図書館」という静謐な舞台で繰り広げられる論理の応酬、そして最後に待ち受ける驚愕の結末——多くの読者が「まさか、そう繋がるとは!」と叫んだのも納得なのだ。
👥主な登場人物
🏫 風ヶ丘高校
裏染 天馬(うらぞめ てんま)
風ヶ丘高校の“校内探偵”。一見するとアニメオタクで無気力な高校生ですが、その頭脳は天才的。今回も警察のアドバイザーとして、図書館で起きた難事件の謎を論理で解き明かします。
袴田 柚乃(はかまだ ゆの)
風ヶ丘高校1年生。試験勉強のために図書館へ行った矢先、事件に巻き込まれることに。裏染天馬と行動を共にし、彼の推理を支える相棒的存在です。
野南 早苗(のなみ さなえ)
女子卓球部の1年生で、柚乃の友人。短編集ではお疲れさまでした。シリーズを通して安定の癒し枠。
佐川 奈緒(さがわ なお)
女子卓球部の部長。文武両道で努力家。その真面目さゆえに、他者の“裏”を見抜けない一面も。
向坂 香織(さきさか かおり)
新聞部部長で、裏染の幼なじみ。情報収集能力と行動力を持ち合わせた“仕掛け人”。
倉町 剣人(くらまち けんと)
新聞部副部長。自由奔放な部長・香織の暴走を止める苦労人。
梶原 和也(かじわら かずや)
演劇部部長。青春を最も謳歌しているキャラ。舞台上でも事件でも、常に目立つタイプ。
針宮 理恵子(はりみや りえこ)
二年生。物語の中で“成長”を遂げたキャラ。彼女の変化は夏の終わりの象徴的シーン。
八橋 千鶴(やつはし ちづる)
元生徒会副会長。腹黒で策略家だが、裏染にだけは逆らえない。
城峰 有紗(しろみね ありさ)
図書委員長。文学好きで図書館に通い詰める少女。事件の中心にいる“知識の番人”。
📚 図書館とその関係者
那須 正人(なす まさと)
風ヶ丘図書館の司書。若く真面目な青年で、誠実な人柄が読者の共感を呼びます。
上橋 ひかり(うえばし ひかり)
司書の女性。清楚な見た目の裏に、静かな決意を秘めています。
久我山 卓(くがやま すぐる)
通称“レノンさん”。独特な存在感を放つ司書。
寺村 輝樹(てらむら てるき)
年配の司書。人当たりが良く、事件の鍵を握る過去を知っている可能性も…?
梨木 利穂(なしき りほ)
司書兼館長。完璧主義で神経質。図書館を守る責任感が強い人物。
桑島 法男(くわじま のりお)
元司書。退職後も図書館に関心を持つ謎の人物。
城峰 恭助(しろみね きょうすけ)
有紗の従兄で横浜国大2年生。図書館の常連で、事件に深く関わる青年。
城峰 美世子(しろみね みよこ)
恭助の母で有紗の叔母。シングルマザーとして強く生きる女性。
明石 康平(あかし こうへい)
恭助の友人で大学生。アカペラサークル所属。自由人タイプ。
🎓 緋天学園
裏染 鏡華(うらぞめ きょうか)
裏染天馬の妹で中等部3年生。兄を尊敬しつつも、柚乃を密かにライバル視している。
忍切 蝶子(おしきり ちょうこ)
緋天学園の卓球部員で、関東最強の女子選手。佐川への挑戦はいつも全力。
👮♂️ 警察関係者
仙堂(せんどう)
県警捜査一課の叩き上げ警部。理屈っぽい天馬に何度も振り回されるが、信頼もしている。
袴田 優作(はかまだ ゆうさく)
柚乃の兄で同じく捜査一課。冷静で頼りになる刑事。妹と天馬の関係には少し複雑な感情を抱く。
白戸(しらと)
保土ヶ谷署の署員。現場での観察眼が鋭く、地味ながら重要なポジション。
💡推しポイント
📚 日常の場所が舞台
本作の舞台は、誰もが一度は訪れたことのある「図書館」。静けさと秩序の象徴であるその空間で殺人事件が起こることで、現実とフィクションの境界が曖昧になり、読者は一瞬で非日常へと引き込まれるのだ。“静寂の中の惨劇”というギャップが、物語全体の緊張感を高めているぴよ。
🤔 ダイイングメッセージの再構築
今回の事件を解く鍵は、現場に残された2つのダイイングメッセージ。一見すると矛盾しているその内容を、裏染天馬がまったく新しい角度から読み解いていくのだ。古典的なトリックを現代的な発想で再構築する青崎有吾の手腕が光るポイント。“ダイイングメッセージとは何か”という概念そのものを問い直す展開に、唸ること間違いなしぴよ。
🕵️♂️ 天才探偵と魅力的なキャラクター
探偵役の**裏染天馬は、天才的な推理力を持ちながらも社会不適合気味な変わり者。警察のアドバイザーとして事件に関わり、論理と思考だけで真実へと迫りるのだ。相棒の袴田柚乃との軽妙なやり取りも健在で、彼女の視点を通じて描かれる天馬の“人間味”も本作の見どころ。さらに新キャラクターや既存キャラの掘り下げもあり、シリーズファン必読の一作となっているぴよ。
📖 『図書館の殺人』
裏染天馬シリーズ、今回もやってくれたぴよ……!😳💥 「図書館」という静謐な舞台で繰り広げられる論理の応酬、そして最後に待ち受ける驚愕の結末——多くの読者が「まさか、そう繋がるとは!」と叫んだのも納得なのだ。
🔎 読者への挑戦
裏染天馬が挑むのは、閉館後の図書館で起きた密室殺人。
あなたは、彼より早くこの「2つのダイイングメッセージ」の意味を解き明かせるだろうか──?
- ダイイングメッセージの解読: 現場に残された「く」と「○」。この2つの記号が示すものとは? なぜ2つ存在したのか?
- K氏の行動: 図書館に忍び込んだK氏は、開いているはずのないドアに気づかなかった。彼は何を見落としていたのか?
- 被害者の従妹: 事件当夜、偶然にも図書館の前でK氏と遭遇。果たしてこれは本当に偶然だったのか?
- 動機の謎: 犯人の行動には、どこか不自然な影。裏染の推理をなぞる前に、あなた自身の「論理」で真相を組み立ててみてほしいのだ。
🧩──あなたは、裏染天馬に勝てるぴよ?
🔓 真相を見る(クリックして開く)
⚠️ 以下、ネタバレ注意ぴよ!
犯人は──城峰美世子なのだ!
事件の鍵は、「2つのダイイングメッセージ」とK氏の行動の矛盾。
被害者が残した「く」と「○」という記号は、
犯人が“自分以外の誰かを犯人に見せかけようとした”偽装の証だったのだ。
また、K氏が図書館に忍び込んだとき「開いているはずのないドア」に気づかなかった理由──
それは犯人が先に侵入していたから。つまり、すでに現場は「作られた密室」だったのだ。
裏染天馬の冷徹な推理がすべての矛盾を貫き、
真犯人の“計算された偶然”を暴く瞬間──まさに知性の勝利なのだ📖🧠
🐧なぞ九郎のひとこと
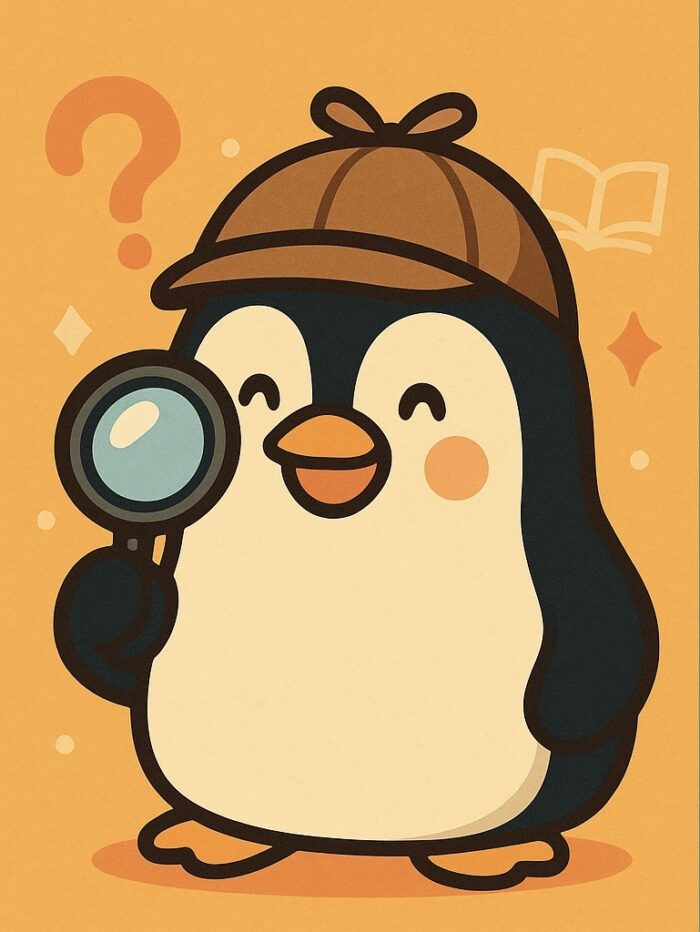
裏染天馬シリーズ、今回もやってくれたぴよ……!😳💥 「図書館」という静謐な舞台で繰り広げられる論理の応酬、そして最後に待ち受ける驚愕の結末——多くの読者が「まさか、そう繋がるとは!」と叫んだのも納得なのだ。
特に秀逸なのは、残されたわずかな物証と状況から導き出される推理の精密さ。 青崎有吾氏の作品に共通する“論理の美しさ”が本作でも際立っており、犯人の動機やトリックも最後まで一貫して筋が通っているぴよ。驚かされながらも、「なるほど!」と納得できるのがこのシリーズの真骨頂なのだ。
さらに、キャラクターたちの魅力も忘れてはいけないぴよ。 天馬の天才ぶりと人間臭さ、柚乃との信頼関係、そして風ヶ丘高校の仲間たちとの青春の一幕が、推理劇に温かみを添えている。 単なる謎解きだけでなく、青春群像劇としての完成度も非常に高いぴよ。
論理も感情も満たされる—— 『図書館の殺人』は、まさにシリーズの中でも“知と情の融合”を極めた一冊なのだ📖✨
📝 まとめ
『図書館の殺人』は、青崎有吾さんによる「裏染天馬シリーズ」第4弾(長編3作目)。
シリーズの特徴である緻密なロジックと青春群像の魅力が一層深化した一冊なのだ📚
静寂の中に知的スリルが走る“図書館”という舞台で、
裏染天馬は2つのダイイングメッセージに隠された真実へと迫っていく。
論理を極めた天才探偵と、彼を支える柚乃のコンビが導く結末は、読後の満足感抜群ぴよ✨
「日常×本格ミステリ」の融合を堪能できる傑作であり、
青崎作品の魅力──驚き・知性・キャラクターの温かみ──がすべて詰まっている。
本格派ミステリ好きも、青春小説好きも、どちらも満たされること間違いなしなのだ🕵️♂️💡
📖 『図書館の殺人』
裏染天馬シリーズ、今回もやってくれたぴよ……!😳💥 「図書館」という静謐な舞台で繰り広げられる論理の応酬、そして最後に待ち受ける驚愕の結末——多くの読者が「まさか、そう繋がるとは!」と叫んだのも納得なのだ。